 Newsletter
Newsletter
AI NEWSLETTER Vol.03 みんなで「同じものを見る」?
2017年4月24日AI Newsletter第三回です。
前回はリーダーの最も重要な仕事について話しました。
今回もチームを率いるリーダーが仕事上で心がけるべきポイントについてお話ししたいと思います。
みんなで「同じものを見る」?

リオオリンピック閉幕で見えた、心を一つにする方法
2016年の大きなイベントと言えば、やはりリオオリンピックだっと言えるのではないでしょうか。タイでは重量挙げの選手が金メダルを獲得しました。また、ベトナムで史上初めて金メダルの獲得者が出るなど、東南アジアの躍進が感じられるオリンピックでした。
そのリオの閉会式で話題になったのが、次回開催地の東京のプロモーションビデオです。ドラえもんやキャプテン翼が登場した後に、日本の安部首相がマリオ姿で登場する。多くの国々から賞賛を浴びた演出でした。
翌日、タイ人のスタッフや友達から「日本のPRはとても良かった!2020年は東京に行きたい!」と声をかけられ、私もとてもうれしい気持ちになりました。このように「みんなで同じものを見る」という体験は人の心を一つに する効果があります。会社の中で時々行われる周年行事やイベントなどは、定期的に社員を一堂に集めて皆で同じ情報を共有することで、会社の方向性を一つにするために行われるわけです。

人は「見たいようにものごとを見る」
それにしても同じ会社でいつも一緒に働いているのに、なぜわざわざこんなことをする必要があるのでしょうか?「そんなことしなくても、いつも同じ情報を共有できているよ」と思う人もいるのではないでしょうか。
実は、人間は同じものを見ているようで実際には見ていないということはたくさんあります。例えば心理学の有名な実験で「ルビンの壺」というものがあります。
同じ絵を見ても、「これは壺だ」「これは人の顔だ」という人が存在します。同じものを見ても人によって捉え方が違うわけです。こういうことが 組織の中では頻繁に起きています。
例えば何かのプロジェクトで問題が起きているとして、同じ事象を見ていても「これはお客さんが悪いのだから我々の問題ではない。放っておくべき。」と捉える人と、「これは我々の問題だから、真摯に対応すべき」と捉える人に分かれます。その結果取られるアクションは180度変わってきます。
また、「人は見たいようにものごとを見る」という習性があります。上記の例でいけば、「自分の身を守りたい」と無意識に思っている人は、「悪いのはお客さんだ」と捉えます。「問題が起きても解決してそこから学んでいこう」と思っている人は「我々にも問題があったのでは?」と捉えます。自身の価値観がものごとの捉え方に反映されるわけです。組織には様々な価値観の人が居ますから、こうして組織の認識はゆがんでいきます。
ファクトに基づき、認識のギャップを埋める
リーダーの大切な仕事は、「みんなで同じものを正しく見る」ことで組織の認識を揃えていくことにあります。
そのために必要なことの一つは、「ファクト(事実)」に基づく議論をすることです。「言った・言わない」の議論 に終始するのではなく、もし問題があったのであれば、「いつ・誰が・何をしたのか」、をファクト(事実)とエビデンス(証拠)を元に議論することです。繰り返しますが、「人は見たいようにしかものを見ない」ので、そうした事実ですら記憶の中でゆがめてしまうのが人間です。それゆえに、リーダーはエビデンスを探し、「事実は何か?」 にフォーカスする必要があります。
もう一つは、「言語による認識ギャップをなくす」ことです。私が仕事をするタイでは、タイ語・英語・日本語、と各種言語が混じることにより組織運営の困難さが日本よりも高いと感じます。他のアジアの国々でもそうでしょう。
先日、ある企業で「チームビルディング」というテーマで日本人とタイ人で議論しましたが、よくよく議論すると、 イメージしていることが180度違うことに驚きました。あるタイ人の方は「チームビルディング」は「仕事を離れ、楽しくみんなで過ごす」ことでチームを活性化するイメージを持っていました。対して日本人の方は、「真剣に集中して議論して、結束を強める」ことをイメージしていました。このように同じ言葉でも捉え方は全く異なることはたくさんあり、日々様々なすれ違いが我々の組織では起きています。
コミュニケーションは「面倒くさい」
リーダーの大切な仕事は、「みんなで同じものを正しく見る」ことで組織の認識を揃えていくことにあります。こうしたことを防ぐには、「複数言語」でのコミュニケーションを頑張って行うしかありません。例えばタイのある日系企業では、毎回の会議の議事録を日本語、英語、タイ語、の3言語で用意して展開しているそうです。こうしたことは大変な労力を要しますが、組織の中で「同じものを見る」ということをするうえでは必要な労力かもしれません。こうした努力にショートカットはなく、リーダーのコミットメントが問われる部分だと言えます。そもそもコミュニケーションとは「面倒くさい」ものなのです。
このブログも、わざわざ「日本語」と「タイ語」で同時に発信することで、今までにない共通理解がタイ人と日本の間で生まれるとよいなと思い、チャレンジを続けています。皆さんも日々のミーティングや研修などで、「今、私たちのチームは同じものを見れているだろうか?共通理解が作れているだろうか?」と問いかけ、意識してみることをお勧めします。
Asian Identity の チームビルディング

Asian Identityでは、各部門やチームごと、またプロジェクトチームメンバーなど様々なチーム ビルディングのサポートを提供しています。
メンバー全員がお互いが働く⽬目的やストーリーなどを共有し、 チームとして共通のビジョン、目標を持って進んでいくことを目指します。
「地頭・Logical Thinking 研修」
5月に開催します「JI-ATAMA Logical Thinking Workshop(JAL)」では「考える」ことが求められる業務に従事するマネージャー / プレーヤーに向けた公開型のワークショップです。業務の経験を積めば積むほど、我々が取り組むべき仕事はより難しく複雑なものになっていきます。これらの仕事を成功させるには経験や知識だけでは⾜足りません。必要なのは、⾃自分で考えて答えを探し出す⼒力力です。本ワークショップでは様々なアクティビティを通して思考を整するスキルを⾝身につけていくことで、「直感ではなく根拠を持って判断できる」「相手に論理的なコミュニケーションができる」状態を目指します。
Continue reading
-

26 3月, 2021
Newsletter AI NEWSLETTER Vol.46 「ボーナスでモチベーションは高まるか?~外発的動機と内発的動機」
AIニュースレター、46号です。 この時期、人… -
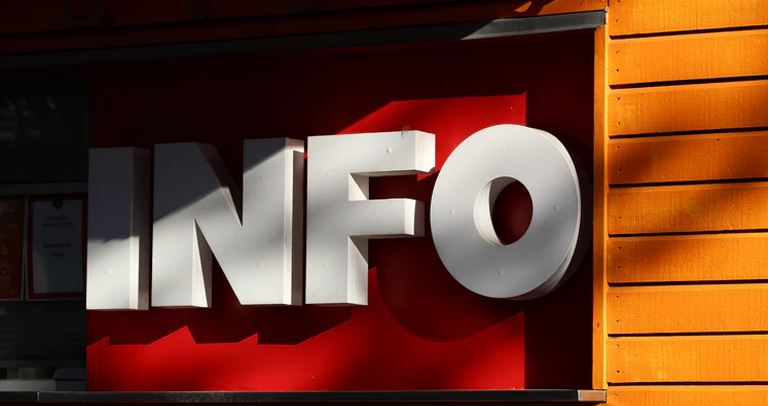
18 8月, 2021
Newsletter AI NEWSLETTER Vol.48 「全ては相対的である ~情報に振り回されないための心構え」
AIニュースレター、48号です。 「全ては相対的である ~情… -

25 4月, 2024
Newsletter AI NEWSLETTER Vol.58 タイの離職率はどの程度が適切なのか?
Asian Identityニュースレター、58号です。 本…
 中村 勝裕
中村 勝裕